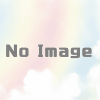【風邪の特効薬】大発見!家系ラーメンの秘密
家系ラーメンが「究極の風邪薬」としてテレビで紹介され、真偽のほどはどうなのかと一時期話題になりました。
そもそも風邪にラーメンが効くなんて話、なかなか信じがたい話ですよね。
私はラーメンが好きなので、健康にいいと聞いたら毎日食べてしまいそうです。
今回はその家系ラーメンの秘密に迫りたいと思います。

「家系ラーメンとは」
家系ラーメンが風邪に効くという話の前にそもそも家系ラーメンとは何かを説明します。
家系ラーメンの始まりは、1974年に神奈川県横浜市新杉田にオープンした「吉村家」です。当時、長距離トラックの運転手を務めていた店主が「九州の豚骨と東京の醤油を混ぜたらうまいんじゃないか」と思い立ったことがきっかけでオープンするに至りました。
特徴としては「鶏と豚骨から取る濃厚なスープ」「モチモチで太いストレート麺」「チャーシュー、海苔、ほうれん草などの具材」が挙げられます。
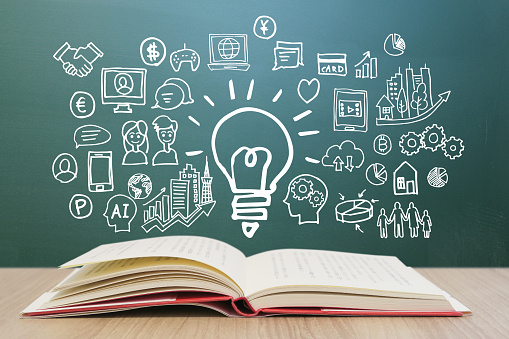
「風邪に効くとされる理由」
鶏油:炎症を抑える効果
家系ラーメンのスープを特徴付けている、鶏油(チーユ)。鶏の脂肪分を熱して抽出し作られています。
その鶏油に含まれる「グリシン」というアミノ酸の一種がのどの腫れを抑えるのに効果的とされています。
海苔:粘膜を強くする効果
ラーメンのトッピングに欠かせない海苔も風邪と戦うのにぴったりな食材。
粘膜は病原菌を寄せ付けないようにするバリアの役割を果たしているのですが、そんな粘膜を生成するのに欠かせない栄養素であるビタミンAが豊富に含まれています。
ほうれん草:免疫力を高める効果
ほうれん草にはビタミンCが豊富に含まれています。
ビタミンCは、 ウイルスに攻撃する白血球の動きを活発にするほか、体内で感染した有害菌を除去するなどして免疫力を高める作用があります。

メリット・デメリット
家系ラーメンの具材である、ほうれん草に含まれるベータカロテン(ビタミンA)は粘膜を保護する作用が期待できるため、風邪予防にはおすすめの食材です。ただ、ビタミンCはゆでることで半減しますし、海苔1枚に含まれているビタミンAは輪切り人参1枚(3g)と比べても10分の1程度と少量です。トッピング量が少なければ、大きな効果は期待できません。
豚骨と鶏油に含まれるアミノ酸のグリシンは水溶性なので、スープにどれくらい含まれているかがポイントでしょう。ただ、グリシンを多く摂取するためにはスープを多く飲まなければなりません。そうなると、逆にカロリーや塩分のとりすぎになることも考えられます。
しかし、ニンニクに含まれるアリシンによる殺菌や疲労回復の効果は、風邪予防にいいと思います。生姜も、加熱することでジンゲロールがショウガオールという、より内側から熱を発生させる物質に変わるため、ラーメンに入れるのはいい方法であるといえます。

にんにく大量の二郎系ラーメンも風邪に効く?
つまり、風邪に効くかどうかは、ラーメンそのものではなく具材や薬味にポイントがあるということになります。そうなると、家系ラーメンよりもたっぷりの野菜やチャーシューが盛られ、にんにくを大量にトッピングできる「二郎系ラーメン」のほうが風邪に効果があるのではとも思えます。
確かに、二郎系ラーメンに入っているもやしやキャベツには食物繊維が多く含まれ、油脂の吸収をゆるやかにする効果が期待できます。また、チャーシューとにんにくの組み合わせもおすすめです。豚肉に多く含まれるビタミンB1は、にんにくのアリシンによって吸収率が高まり、疲労回復に効果があるからです。とはいえ、風邪の予防として考えるのなら、ベータカロテン(ビタミンA)が入っていて、カロリーの負担も少ない家系ラーメンのほうがいいかもしれませんね。

以上、風邪の特効薬と言われる、家系ラーメンの秘密です。様々な食材の相乗効果が一見すると不健康そうに見えるものでも、意外と体に良かったりするものなのですね。
みなさんも風邪には気を付けておいしくラーメンを食べましょう。